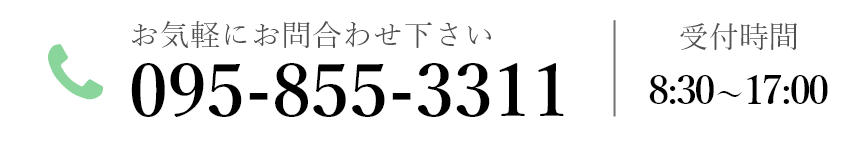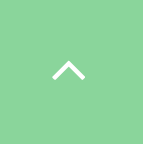院長エッセイ~育む~
- HOME
- 院長エッセイ~育む~
植物は環境次第で育ち、花を咲かせ、実がなります。脳神経は植物のように育む必要があります。
日々の生活の中でヒントにして頂ければと思い、私自身の取り組み方などを綴っています。
2026年2月
情緒機能
「情緒不安定」という言葉がありますが、誰にでも起こることです。情緒の管理について考えてみます。先月は右脳左脳の話でしたが、これは脳の構造的な分類による役割の分担を意識するということでした。今回は脳の機能的な分類です。脳機能は、1.認知機能 2.情緒機能 3.社会的機能 4.自己認識機能に分類されます。認知機能は五感などによる知覚、記憶、思考、言語、推測などです。情緒機能は何かに反応する心の動きですが、動物的本能的なもので、自律神経を介した身体表現としても現れます。感情とは少し意味が違います。感情がこじれるとは言いますが、情緒がこじれるとは言いません。社会的機能は社会で生きるために学んでいく機能です。自己認識機能は自分が自分であるという認識で行動する機能です。
情緒と感情は重なるところもありますが、違います。情緒は人間以外の動物でも普通にある瞬間的なものですが、動物は泣いたり笑ったりしませんし、くよくよもしません。ワニの涙は単なる生理的反応です。笑っているように見えるペットは飼い主の心の反映です。しっぽを振ったり、目を大きくしたり、ドキドキしたりは情緒反応です。感情は情緒に伴った認知機能が関係し、記憶や経験などの個人的文脈(解釈)により起こる情緒より長く続く脳の反応です。従いまして、情緒を認知機能で管理することが感情コントロールになります。つまり認知機能を高める、すなわち学習していくことが必要になります。
情操教育といえば、音楽、美術があげられますが、認知機能を高める教育、すなわち小学校で習うすべての教科が情操教育になります。情緒を操るという文字どうりで、子供たちは少しずつ大人になっていき、それに伴って社会的機能も高まります。さらにこれらが組み合わさって自己認識機能が高まり、自信にもつながっていきます。見知らぬものに出会うと、情緒機能が働きますが、理解力が深まれば好き嫌いなどの感情から味わいに変わっていきます。反対に「いつものやつ」に触れると情緒は安定しますので、ルーチンを持つのは効果的です。
いくつになっても勉強は認知機能、情緒機能の管理に役立ちますので、倦うまず弛たゆまず続けましょう。
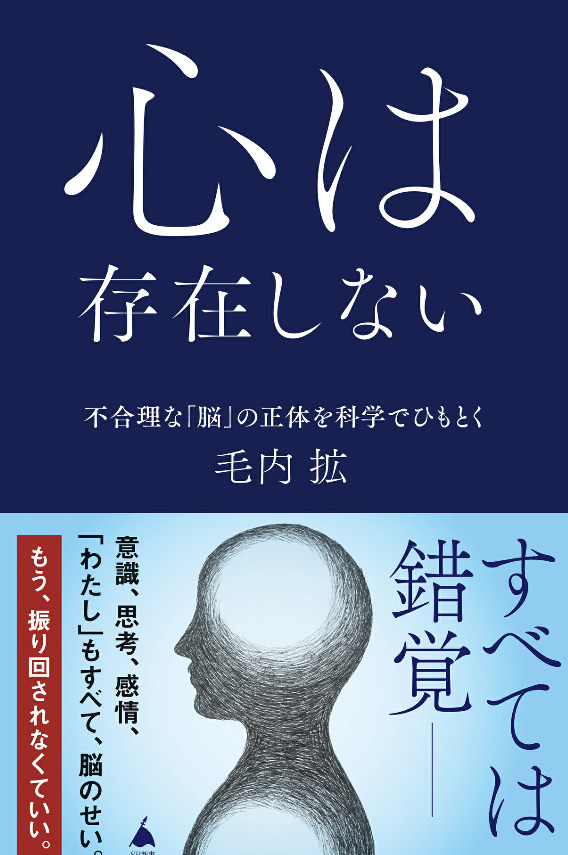
バックナンバー
過去に掲載されたエッセイ&語録をご覧になれます。
ご覧になりたい月をクリックしてください。
2026年
2025年
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年